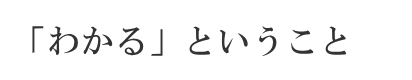 |
||
| 「解」という文字をよく見ると、これは「牛」の「角」を「刀」で切り取ることだと気づくだろう。いや、気づかないまでも、そう云われれば、なるほどと思うに違いない。つまり「解」とは、牛にかぎらず、とにかく大きな塊を解体することで内容が「わかる」ことだ。 むろん解体して部分がよくわかったからと云って、全体がわかるというものでもない。部分が有機的に組み合わさると、どの部分にもなかった新たな要素が生まれたりもするからだ。しかし直感で全体を感じとる能力の衰えてしまった人間は、どうしても初めは部分にこだわらざるを得ない。あらゆる部分に習熟し、それから再び全体を把握できるようになるのだろう。そう思いたい。 『荘子』 あまりに見事な庖丁さばきに感動した 牛を解体しはじめた頃は、目に映るのは牛ばかりでした。つまり、どこから手を付けたらいいか、見当もつかなかったのです。しかし三年も経つと、もう牛の全体は目につかなくなりました。近頃はどうやら精神で牛に向き合っているらしく、目では見ていません。感覚器官による知覚もやみ、どうも精神の自然な働きに従って行動しているのです。天理に従い、牛刀は自然に大きな隙間に入っていきますし、そのまま大きな空洞に沿って無理なく進みます。靱帯や腱に庖丁がぶつかることもありませんし、大きな骨にぶつかることは尚更ありません。 なんとも名人芸だが、ここで丁さんが求めてきたのは、「技」ではなく「道」だという。荘周にすれば、これこそ全ての「道」に共通するプロセスだと言いたいのだろう。 まずは対象に向き合うわけだが、初めは明らかに相手に圧倒されている。「目に映るのは牛ばかり」という状況である。しかし三年も経つと状況は大いに変化してくる。さらりとそう書いてあるが、ここには幾つもの型も覚え、それを繰り返し練習する時間があったはずである。 無意識にいろんな動作ができるようになってくると、そこに一つの「自然」が生まれてくる。「 自然な人間の前に、ようやく対象の自然も姿を現す。すると隙間も自ずから見えてきて、すかさずそこに刀が入っていく。まるでイチローのバットのように、牛刀は嫌でも行くべきところにしか行かない。だから丁さんの庖丁は十九年使っても刃こぼれ一つしない。普通はどんなに腕のいい料理人でも一年使うのが限度だというのに、である。 およそ「道」と名のつくものは、武道はむろんのこと、茶道も生きた人間が相手だ。丁さんが死んだ牛を解体するようなわけには行かないだろう。さまざまに変化しつづける相手に応じるためには、中途半端な型はむしろ邪魔になってしまう。すっかり身につき、型があることさえ忘れる境地まで行かなくてはなるまい。 お茶に喩えれば、なまじ中途半端に学ぶと、お茶の素養のない人を接待することができなくなるようなものだ。なにも知らなければとにかく相手に喜んでもらおうと発想できるのに、学んだ型が崩せないため、かえって相手に居心地の悪さを感じさせてしまう。 学んだ型は、最終的にすっかり「身につき」、「忘れた」ようにならなくてはならない。「身につく」とは、即ち「忘れること」、忘れてもできてしまうこと、なのである。 そのような境地が、『荘子』には「 「鬼に金棒」と思えるほどの何かの道に習熟しても、使わないときにまで金棒を引きずりまわすようでは甚だ鬱陶しい。良寛が風雅くさき話、茶人くさき話を戒めたのはそのことである。 ああ、さても「わかる」ことは難しい。 |
||
 |
||
| 「なごみ」2011年2月号 | ||
| |
||
| |
||