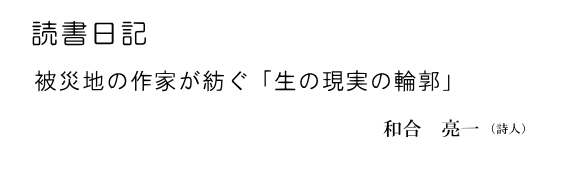 |
||
| 玄侑宗久さんの新著『光の山』(新潮社、1470円)は、震災後に初めて出された玄侑さんの短編小説集である。福島の三春に住む作家の、震災後の経験と思いが込められた作品が、六つ収められている。 震災後に玄侑さんとお会いする機会があった。その時に創作の話になった。玄侑さんはご自身のお寺を避難所にしたり、復興委員の仕事や講演活動などもあったりと、多忙を極めて、なかなか小説を書く方へ気持ちが向かなかったが、次第に短いものから生まれるようになったと話していた。 最初の「あなたの影をひきずりながら」は「見開き4ページの特に短いものである。これは震災の年の夏に発表されている。例えばこのような一場面がある。 「南相馬の派出所の若い警官は困り果てていた。『ダメだよお爺ちゃん、ここから南には行けないし、牛はもう死んでいるよ』『大丈夫だ。放射能ひゃらなんにも感じね。牛が死んだら俺も死ぬ』『ダメだって』」 福島という被災地の現場での、真に迫る声が書かれている。現実を小説という形で描き続けながら、未曾有の震災を経験して衝撃と傷を深く受けてしまった心と作家意識とを、静かに少しづつ回復させていこうとする様子が感じられた。 たくさんの悲しみと困難を抱えた災いと向き合い、それでも目の前の今を書き続ける姿勢がある。震災後に書かれた他の小説には見当たらないような生の現実の輪郭が描かれている。いろいろなことを思い出して涙ぐんでしまいそうになる。 6編のうち「蟋蟀」や「アメンボ」「拝み虫」など、タイトルに虫が登場してくるものが多い。大事なところで虫たちの姿が、それぞれに何らかのメッセージを人間たちに与えてくれているかのようである。 「そのカマキリに、聖子を感じた。まさか津波で死んだ聖子の生まれ変わり、とまでは思わない。しかしたとえばカマキリが独特の戦闘的な姿勢で身構えると、山口には聖子の『よっしゃ』と喜ぶ威勢のいい声が聞こえたりする」 亡くなった人へのやるせない思い、あるいは他のところでは放射能という目に見えないものへの恐怖や悲しさが、地べたを生きるごく小さな存在の確かな命に目を向けさせているかのようだ。 震災から2年がたち、早くも風化の危機にさらされていると感じる。私たちの心の空白を一つずつ丁寧に埋めていこうとするかのようにして物語る筆先が、いまだ出口の見えない福島の寄る辺なさを、ありのままそのままに伝えてくれようとしている。 |
||
 |
||
| 「週刊エコノミスト」6月18日号 (毎日新聞社) | ||