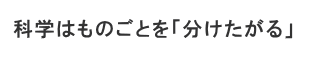| |
|
|
| |
 |
|
| |
取材・文:倉田 波 / 写真:栗原克己 |
|
| |
|
|
| |
「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」
この世も、そして私たちの体も。システムを保ちつつ変化する。
そこでは「揺らぐこと」が最強の戦略なのだ。 |
|
| |
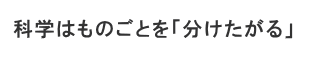 |
|
| |
 福岡さんの『生物と無生物のあいだ』は衝撃的でした。理系の方が、こんな繊細な文章でこういうことを書くのかと。文芸と科学の合体ができる方が現れたと思いました。 福岡さんの『生物と無生物のあいだ』は衝撃的でした。理系の方が、こんな繊細な文章でこういうことを書くのかと。文芸と科学の合体ができる方が現れたと思いました。
 過分なお言葉です。私には、玄侑さんのほうが文系と理系を自由に行き来されているように思えます。 過分なお言葉です。私には、玄侑さんのほうが文系と理系を自由に行き来されているように思えます。
 でも、科学的なことを語る場合、人は理系の人の言葉を信用するんですよ(笑)。 でも、科学的なことを語る場合、人は理系の人の言葉を信用するんですよ(笑)。
 なぜでしょうね(笑)。 なぜでしょうね(笑)。
 人間はものごとをわかりたいと願うとき、全体を部分に分けて考えようとしますよね。現実には存在しない境界を設け、ある部分を切り取って検証したり、分析したりして理解しようとする。理系の方の書くものはそうした欲求に応えているんじゃないでしょうか。ただ、切り分けることでわからなくなる部分もたくさん出てくるわけですが。 人間はものごとをわかりたいと願うとき、全体を部分に分けて考えようとしますよね。現実には存在しない境界を設け、ある部分を切り取って検証したり、分析したりして理解しようとする。理系の方の書くものはそうした欲求に応えているんじゃないでしょうか。ただ、切り分けることでわからなくなる部分もたくさん出てくるわけですが。
 そうですね。理系の専門教育が主に何をやるかというと、ものを「分けて名付ける訓練」なんです。学生に顕微鏡で細胞を見せてスケッチさせると、最初はうまく描けない。どこまでが一つの細胞かもわからないし、名もない粒や筋がユルユルと揺らぐ姿を写すと、子どもが描いたような途切れ途切れの線になってしまう。ところが、細胞には核があり、なかにDNAが折りたたまれ……と部分に分けて名前を与えていくと、描けるようになります。そうやって境界線を引き、名付けることで、一見、世界は整理されたように見える。でも、そのために見えなくなるものは少なくないんです。 そうですね。理系の専門教育が主に何をやるかというと、ものを「分けて名付ける訓練」なんです。学生に顕微鏡で細胞を見せてスケッチさせると、最初はうまく描けない。どこまでが一つの細胞かもわからないし、名もない粒や筋がユルユルと揺らぐ姿を写すと、子どもが描いたような途切れ途切れの線になってしまう。ところが、細胞には核があり、なかにDNAが折りたたまれ……と部分に分けて名前を与えていくと、描けるようになります。そうやって境界線を引き、名付けることで、一見、世界は整理されたように見える。でも、そのために見えなくなるものは少なくないんです。
 動物行動学者の故・日高敏隆さんが書いておられるんですが、小学校低学年の子にアリの絵を描かせると、多くの子が頭と胴だけを描くというんです。アリには頭、胸、腹があり、胸の部分から六本の肢が生えている。でも、実物を見せても、やっぱり頭と胴、それに四本の肢が胴から生えているように描く。子どもの意識にはおそらく頭、胸、腹の区分がないから、実物を見てもも見えない。これは、境目や部分というものが、なんらかの符丁なしでは認識されないということじゃないですか。 動物行動学者の故・日高敏隆さんが書いておられるんですが、小学校低学年の子にアリの絵を描かせると、多くの子が頭と胴だけを描くというんです。アリには頭、胸、腹があり、胸の部分から六本の肢が生えている。でも、実物を見せても、やっぱり頭と胴、それに四本の肢が胴から生えているように描く。子どもの意識にはおそらく頭、胸、腹の区分がないから、実物を見てもも見えない。これは、境目や部分というものが、なんらかの符丁なしでは認識されないということじゃないですか。
 ああ、そうですね。 ああ、そうですね。
 自分と同じように顔があり、あとは動くから肢を付けるというのは、自然に接したときの実感だと思うんです。研究には区分が大事でしょうし、大人の理解には名前や概念が重要ですが、区分というのは、そもそも現実を言葉で分けたがる人間の強引な線引きですよね。 自分と同じように顔があり、あとは動くから肢を付けるというのは、自然に接したときの実感だと思うんです。研究には区分が大事でしょうし、大人の理解には名前や概念が重要ですが、区分というのは、そもそも現実を言葉で分けたがる人間の強引な線引きですよね。
 生物の体は一つひとつの細胞が少しずつ変化しながら発生していったものですから、本来、分けることはできないんですよね。人体についても、私たちはつい、心臓や肝臓が部品みたいにはめ込まれてできているように思ってしまいますが、心臓をその機能ごと取り出そうとすれば、体全体に広がる血管や神経まで切り出さないとならない。科学は対象を要素に分けるところからスタートしますが、世界はもともと、切れ目なくつながっているんです。 生物の体は一つひとつの細胞が少しずつ変化しながら発生していったものですから、本来、分けることはできないんですよね。人体についても、私たちはつい、心臓や肝臓が部品みたいにはめ込まれてできているように思ってしまいますが、心臓をその機能ごと取り出そうとすれば、体全体に広がる血管や神経まで切り出さないとならない。科学は対象を要素に分けるところからスタートしますが、世界はもともと、切れ目なくつながっているんです。
 その意味で、福岡さんのご本のタイトルでもある「世界は分けてもわからない」という言葉は、科学を打ち据えるものにも思えますね。 その意味で、福岡さんのご本のタイトルでもある「世界は分けてもわからない」という言葉は、科学を打ち据えるものにも思えますね。
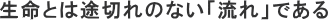
 福岡さんは、生物の体は単なる分子の集まりではない、そこに別のものが加わったとき、それは生命になるとおっしゃっていますよね。そして、そのプラスアルファとは、体を成す要素の「流れ」だと。 福岡さんは、生物の体は単なる分子の集まりではない、そこに別のものが加わったとき、それは生命になるとおっしゃっていますよね。そして、そのプラスアルファとは、体を成す要素の「流れ」だと。
 生物の体を構成する分子は、食物として取り込む分子と絶えず置き換わっています。私たちの体は、そうした分子の流れが一時的に生み出す“よどみ”みたいなもので、生命とはいわば、その流れがもたらすところの効果だといえる。その効果のあり方を、「動的平衡」と呼んでいるんですが。 生物の体を構成する分子は、食物として取り込む分子と絶えず置き換わっています。私たちの体は、そうした分子の流れが一時的に生み出す“よどみ”みたいなもので、生命とはいわば、その流れがもたらすところの効果だといえる。その効果のあり方を、「動的平衡」と呼んでいるんですが。
 仏教でも、命を一つの流れとして捉えます。ある植物が枯れ、それがもとになってまた新しい植物が生えてくる連続を思えば、生命は確かに途切れない流れに違いない。だいたい、生まれる瞬間も死ぬ瞬間も、「ここだ」と示すことはできませんよね。呼吸停止や心停止を死の兆候と見なすのは、人間がつくったり取り決めでしかなくて。 仏教でも、命を一つの流れとして捉えます。ある植物が枯れ、それがもとになってまた新しい植物が生えてくる連続を思えば、生命は確かに途切れない流れに違いない。だいたい、生まれる瞬間も死ぬ瞬間も、「ここだ」と示すことはできませんよね。呼吸停止や心停止を死の兆候と見なすのは、人間がつくったり取り決めでしかなくて。
 その意味で、死はものごとを分ける思想の産物なんですね。動的平衡の視点から見れば、誕生とは、精子と卵子が合わさって別の流れが生じたということだし、死とは、生物の体を構成する六〇兆個の細胞が次第にその平衡状態を失っていく過程です。でも、私たちは、すべての細胞が死に絶える瞬間を見極めることはできない。 その意味で、死はものごとを分ける思想の産物なんですね。動的平衡の視点から見れば、誕生とは、精子と卵子が合わさって別の流れが生じたということだし、死とは、生物の体を構成する六〇兆個の細胞が次第にその平衡状態を失っていく過程です。でも、私たちは、すべての細胞が死に絶える瞬間を見極めることはできない。
 そもそも死という概念自体、仏教とともに入ってきたもので、それ以前の日本にはなかったと思うんです。『古事記』や『万葉集』では、「避る」といっています。生まれてきて、やがて去ってしまった、と。 そもそも死という概念自体、仏教とともに入ってきたもので、それ以前の日本にはなかったと思うんです。『古事記』や『万葉集』では、「避る」といっています。生まれてきて、やがて去ってしまった、と。
福岡さんは『世界は分けても分からない』のなかで、「マッハ・バンド」について触れておられますよね。
 濃い色から薄い色へ連続的に変化する絵を見るとき、人間の目には濃いところをより濃く、薄いところをより薄く見て、そこに存在しないはずの境界を生み出してしまう。その境界に生じる帯をマッハ・バンドといいます。視細胞の性質からくる錯覚なんですが。 濃い色から薄い色へ連続的に変化する絵を見るとき、人間の目には濃いところをより濃く、薄いところをより薄く見て、そこに存在しないはずの境界を生み出してしまう。その境界に生じる帯をマッハ・バンドといいます。視細胞の性質からくる錯覚なんですが。
 生死の境界も、いわば人間が生み出したマッハ・バンドではないかと思うんです。色のなかに境界を見るというのは、虹もそうじゃないですか。 生死の境界も、いわば人間が生み出したマッハ・バンドではないかと思うんです。色のなかに境界を見るというのは、虹もそうじゃないですか。
 はい。虹も連続したスペクトルですが、人間の視覚はそれを五色、七色と分けて見てしまいます。実際、私たちが見ているこの世界は、私たちが勝手につくり出した色の世界なんですよね。 はい。虹も連続したスペクトルですが、人間の視覚はそれを五色、七色と分けて見てしまいます。実際、私たちが見ているこの世界は、私たちが勝手につくり出した色の世界なんですよね。
 植物がなぜ緑に見えるかといえば、光の三原色のうち、緑系の光を反射するからですよね。反射された光が網膜に届き、神経細胞によってさまざまに変換され、最終的に脳内に画像を結ぶ。要するに、あるものが別のものと出合って変化することで、われわれにそのモノの色が見えるようになる。仏教では、このようにすべての現象は無常に変化しつつ、互いに関係し合うことで、生まれたり、消えたりすると考えます。 植物がなぜ緑に見えるかといえば、光の三原色のうち、緑系の光を反射するからですよね。反射された光が網膜に届き、神経細胞によってさまざまに変換され、最終的に脳内に画像を結ぶ。要するに、あるものが別のものと出合って変化することで、われわれにそのモノの色が見えるようになる。仏教では、このようにすべての現象は無常に変化しつつ、互いに関係し合うことで、生まれたり、消えたりすると考えます。
それにしても、命についてこういう表現をする科学者はいなかった。福岡さんのお仕事は仏教的ですよね。心外かもしれませんが(笑)。
 いえいえ。読者の方からも、「福岡さんは仏教徒ですか」といわれたことがあります(笑)。 いえいえ。読者の方からも、「福岡さんは仏教徒ですか」といわれたことがあります(笑)。
一つには、分子生物学はAがBを成し、BがCを成すという因果律で世界を捉えるんです。でも、生命が流れである限り、そこに見える因果律は、一時的に釘づけされたものでしかないですよね。次の瞬間には因と果が逆転しているかもしれないし、因果自体、消えているかもしれない。こういう私の考え方が仏教となじむのかもしれません。ただ、動的平衡をいい出したのはユダヤ人の科学者ですし、世界が流れだという知見は西洋世界からも出ていますから、仏教に限らず、人間が太古から抱いていた世界観かもしれませんけど。
 因果律自体、人間の思考の習慣と見ることもできますね。それがいまの科学のもとになっている。 因果律自体、人間の思考の習慣と見ることもできますね。それがいまの科学のもとになっている。
初期仏教の経典に、「此れ有るとき彼有り、此れ無きとき彼無し」「此れ生ずるに依りて彼生ず、此れ滅するに依りて彼滅す」とあるんです。前者は「同時」で、後者は「異時」、つまり因果律です。因果の存在を一方で認めながら、一方で同時に起こる関係性に目を向けている。この「同時に起こる関係」は科学で扱えないですよね。例えば「自分がある問題を考えていたとき、別件で訪ねてきた人がその問題に触れる」といった現象は説明がつかない。
 そうです。量子力学にはシンクロニシティのような概念がありますが、あまりそこを強調すると、オカルトっぽくなってしまう。いまの色のお話も、仏教では「色」という言葉を相互作用によって生まれる現象の意味で使ってきたわけで、その洞察力はすごいと思います。それに比べて近代科学は、人間が大昔から気付いていたことを別の言葉に置き換えているにすぎない。いわば、後出しジャンケンなんです(笑)。 そうです。量子力学にはシンクロニシティのような概念がありますが、あまりそこを強調すると、オカルトっぽくなってしまう。いまの色のお話も、仏教では「色」という言葉を相互作用によって生まれる現象の意味で使ってきたわけで、その洞察力はすごいと思います。それに比べて近代科学は、人間が大昔から気付いていたことを別の言葉に置き換えているにすぎない。いわば、後出しジャンケンなんです(笑)。
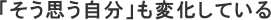
 福岡さんは、生命が流れだということをいうとき、『方丈記』を引かれているでしょう。「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず、よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし」という、あの冒頭は見事だと思うんですが。 福岡さんは、生命が流れだということをいうとき、『方丈記』を引かれているでしょう。「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず、よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし」という、あの冒頭は見事だと思うんですが。
 見事です。玄侑さんも、昨年出版された『無常という力』というご本で、『方丈記』を取り上げていますね。いまなぜ、「無常」を語ろうと思われたのですか。 見事です。玄侑さんも、昨年出版された『無常という力』というご本で、『方丈記』を取り上げていますね。いまなぜ、「無常」を語ろうと思われたのですか。
 現代人にとって、自分が観察者となって移りゆく世の中を眺め、「世界は変化し続けている」と思うことは難しくないですよね。でも、「そう思う自分も変化しつつある」と知ることは簡単ではない。人間は信念、確信、信条といった無常ならざるもので自分を支えようとしますけど、東日本大震災を経て、われわれはもうそういう生き方を改めてもいいんじゃないか。とくに最近は未来に対するシミユレーションが常態化していますが、目標やマニフェストは、無常の目から見れば根拠のない虚像です。むしろ、そのときどきの状況に合わせて揺らぎ、変わっていけることが本当の強さだし、それにはまず無常を受け入れることが大事だと思うんです。 現代人にとって、自分が観察者となって移りゆく世の中を眺め、「世界は変化し続けている」と思うことは難しくないですよね。でも、「そう思う自分も変化しつつある」と知ることは簡単ではない。人間は信念、確信、信条といった無常ならざるもので自分を支えようとしますけど、東日本大震災を経て、われわれはもうそういう生き方を改めてもいいんじゃないか。とくに最近は未来に対するシミユレーションが常態化していますが、目標やマニフェストは、無常の目から見れば根拠のない虚像です。むしろ、そのときどきの状況に合わせて揺らぎ、変わっていけることが本当の強さだし、それにはまず無常を受け入れることが大事だと思うんです。
 何ごとにつけ、「こうだ」と思い込むところに間違いが生じるわけですものね。事実、私たちを構成する分子は無常に入れ替わっていますから、物質レベルで「自分」の一貫性を担保するものは何もありません。唯一、自己同一性を支えるのは記憶ですが、それも常時つくり替えられている。物質的には一年前といまの私は別人だから、極論すれば、過去の約束は守らなくていい(笑)。 何ごとにつけ、「こうだ」と思い込むところに間違いが生じるわけですものね。事実、私たちを構成する分子は無常に入れ替わっていますから、物質レベルで「自分」の一貫性を担保するものは何もありません。唯一、自己同一性を支えるのは記憶ですが、それも常時つくり替えられている。物質的には一年前といまの私は別人だから、極論すれば、過去の約束は守らなくていい(笑)。
 「人が変わった」って(笑)。 「人が変わった」って(笑)。
 ただ、こういう思想を浸透させるには時間がかかるでしょうね。 ただ、こういう思想を浸透させるには時間がかかるでしょうね。
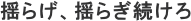
 玄侑さんは復興構想会議のメンバーになっておられますが、ご自身の思想と現場の要請が折り合わないこともあるのではないですか。 玄侑さんは復興構想会議のメンバーになっておられますが、ご自身の思想と現場の要請が折り合わないこともあるのではないですか。
 それはあります。例えば、日本には津波神社のように、自然の驚異そのものを神として祀る場所があります。恐ろしいから祀るという文化や宗教は、恐ろしさをなくしたら途絶えてしまう。だから、怯えは保たなければならないといっても、なかなかご理解いただけません(笑)。 それはあります。例えば、日本には津波神社のように、自然の驚異そのものを神として祀る場所があります。恐ろしいから祀るという文化や宗教は、恐ろしさをなくしたら途絶えてしまう。だから、怯えは保たなければならないといっても、なかなかご理解いただけません(笑)。
しかし一方、二〇メートルの津波が来た地域に二五メートルの防潮堤をつくるかというと、そうはならない。巨大防潮堤を築くのは自然と対峙する発想ですが、それをやれば、そこはもう遊び場ではなくなります。一三~一五メートルの津波が来た相馬港では、七~八メートルの防潮堤をつくることで落ち着きました。何もせずにいられないのは日本文化に対して忍びないという、いじらしい数字だと思います(笑)。
 なるほど(笑)。でも、自然とは、そうやってだましだまし付き合うしかないんですよね。 なるほど(笑)。でも、自然とは、そうやってだましだまし付き合うしかないんですよね。
 いまはまさに、「だましだまし」のような言葉を復権すべくでしょうね。TPPの問題も、被災地がこんな状態のときにテキパキ進めてもらっては困る。「グズグズ、ウダウダ」、時間をかけて検討してほしい。放射能の問題も、検出量ゼロ以上はすべて悪いと決めつけず、「わからない」状態のまま向き合っていく勇気も必要です。放射能は無常のなかにあって無常でないものですが、この国がこれほど多雨であるために、阿武隈川からは毎日五〇〇億ベクレルの放射性セシウムが流れ出ているという。その速度で除染されていると思えば、希望がないわけではありません。海や漁師さんには本当に申し訳ないんですが、これも、無常の力だと思うんです。 いまはまさに、「だましだまし」のような言葉を復権すべくでしょうね。TPPの問題も、被災地がこんな状態のときにテキパキ進めてもらっては困る。「グズグズ、ウダウダ」、時間をかけて検討してほしい。放射能の問題も、検出量ゼロ以上はすべて悪いと決めつけず、「わからない」状態のまま向き合っていく勇気も必要です。放射能は無常のなかにあって無常でないものですが、この国がこれほど多雨であるために、阿武隈川からは毎日五〇〇億ベクレルの放射性セシウムが流れ出ているという。その速度で除染されていると思えば、希望がないわけではありません。海や漁師さんには本当に申し訳ないんですが、これも、無常の力だと思うんです。
 いま私たちは、科学の問題ではなく、科学の限界の問題に直面しているんですね。対処法は人それぞれですが、すぐに「科学的にどうですか」と答えを求めない心のあり方が、この世界に向き合ううえで、いちばん有効であるとも思います。 いま私たちは、科学の問題ではなく、科学の限界の問題に直面しているんですね。対処法は人それぞれですが、すぐに「科学的にどうですか」と答えを求めない心のあり方が、この世界に向き合ううえで、いちばん有効であるとも思います。
玄侑さんがお書きになっているとおり、『方丈記』は冒頭だけでなく、終わりもいいんですよね。無常の世に質素な方丈で暮らすことの満足を語った後、「でも、こういう暮らしを良いものとしてこだわることもまた執着ではないか」といっている。
 そして最後は、「ただ阿弥陀仏の御名を二、三度唱えた」と終わるんですね。これが法然上人みたいに六万回も唱えたとなると、自力になりかねない。二、三度というのは、何もしないよりいいという姿勢です。「防潮堤七メ―トル」と一緒で(笑)。 そして最後は、「ただ阿弥陀仏の御名を二、三度唱えた」と終わるんですね。これが法然上人みたいに六万回も唱えたとなると、自力になりかねない。二、三度というのは、何もしないよりいいという姿勢です。「防潮堤七メ―トル」と一緒で(笑)。
 ほどほどに(笑)。でも、こうした往還、ある種の迷い――先ほど「揺らぎ」といわれた――が人間の世界認識の本当のところでしょうね。 ほどほどに(笑)。でも、こうした往還、ある種の迷い――先ほど「揺らぎ」といわれた――が人間の世界認識の本当のところでしょうね。
 ええ、私たちはいくらでも揺らいでいい、いや、むしろ揺らいだほうがいい。そう思えたら、いまよりずっと楽に、そして強く生きていけると思います。 ええ、私たちはいくらでも揺らいでいい、いや、むしろ揺らいだほうがいい。そう思えたら、いまよりずっと楽に、そして強く生きていけると思います。
|
|
| |
※1 強い光を受け取った視細胞からの信号がコントラストを強調することで起こる錯覚。オーストリアの物理学者エルンスト。マッハが確認した
※2 ルドルフ・シェーンハイマー(1898~1941)
※3 浄土宗の開祖である法然は「南無阿弥陀仏」を1日6万回唱えたといわれる
|
|
| |
|
|
| |
ふくおか・しんいち
1959年東京生まれ。京都大学大学院終了。ハーバード大学研究員、京都大学助教授を経て、青山学院大学教授。サントリー学芸賞受賞の『生物と無生物のあいだ』ほか、『できそこないの男たち』『動的平衡』『フェルメール 光の王国』、阿川佐和子さんとの共著『センス・オブ・ワンダーを探して』など、著書多数。最新刊は『動的平衡2』。今月1月にオープンしたフェルメール全37点のリ・クリエイト作品を一堂に展示した「フェルメール・センター銀座」の監修および館長も務める。 |
|
| |
 |
|
| |
「Fole」2012年2月号(みずほ総合研究所) |
|
| |
|
|