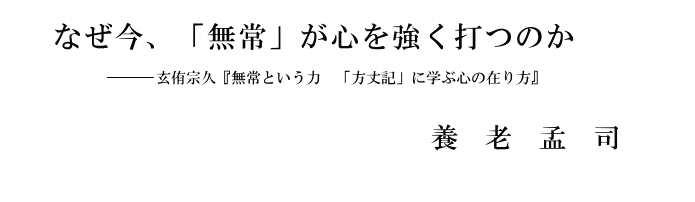 |
||
| 玄侑宗久さんが『方丈記』を論じている。お坊さんに『方丈記』、それこそピッタリ、相性がいいに決まっている。そう思う人もあるかもしれない。でももちろん、玄侑さんがいいたいのは、それだけではない。大切な背景がある。三・一一とそれ以降の東北のことである。玄侑さんのお寺は福島県の三春にある。お寺には被災者も集まっただろうし、さまざまな事情で震災後にも亡くなる方が多かったと聞く。さらに玄侑さんご本人も、お国の復興会議とやらに委員として出ておられたようだから、気持も身体もあれこれ大変だったに違いない。福島だから放射能のこともあって、いまでも大変であろう。そうしたもろもろが、『方丈記』という「よりしろ」を得て結晶化し、この本になった。 『方丈記』にはそういう作用があるのだと思う。よい前例がある。それは堀田善衞の『方丈記私記』である。昭和二十年三月九日夜半から、東京の下町は大空襲を受けた。堀田善衞は当時二十七歳、目黒洗足の友人の疎開先から、炎々と燃え続ける下町方向を見つつ、深川に住む「一人の親しい女」の身を案じていた。そのとき突然によみがえったのが、『方丈記』の記事だった。安元三年(一一七七)の大火に触れて『方丈記』は記す。「その中の人、現し心あらむや」。火災の中の人は、生きた心地がしないだろう、というのである。その追憶から始まって、堀田の場合には、戦災体験と『方丈記』が往復運動を繰り返しながら、一巻の書物となる。 今回の作品は、玄侑宗久の『方丈記私記』といっていいであろう。『方丈記』には、作家の心を深いところで動かす、なにかがある。私は生来野暮で、風流に向かう心はない。でも日本の古典のなかでは、『方丈記』がなぜか自分の心を強く打つことを知っている。玄侑さんもそうだと知って妙に嬉しいのである。 まだ大学勤めで現役の頃、たとえば経団連みたいなところから、「新入社員に勧める一冊」というアンケートを書かされた記憶がある。そのときに、私は『方丈記』と書くのが常だった。なにしろ原稿用紙二十五枚ほど、古典で確実に全文を見たといえるのは、これしかない。むろん半分以上は皮肉である。当時のことだから、これから会社に入って、末は社長か重役か、高度経済成長でお金を儲けて当たり前、そういう若者たちに「ゆく河の流れ」がなんの関係がありますかね。その上、ともあれ古文だから、いかに短いとはいえ、読みにくかろうと思う。その点、今度の玄侑さんの本はたいへん親切で、現代語訳がついている。これならいまの若者でも簡単に読めるではないか。今度は皮肉でなく、経団連に推薦したい。 仁和寺の隆暁法印が、飢饉の際、白骨を含む死者の額に「阿」の字を書いていく。その数、左の京だけで四万二千三百。堀田善衞も玄侑さんもそこを引用している。私も引用したことがある。それをいわば淡々と見つめる目が、鎌倉時代の目である。その目が日本人の心の奥底に隠れている。天災があると、その目が覚めて、あらためて世界を見つめる。玄侑さんの属する臨済宗も、この時代に生まれた宗派といってもいいであろう。そこでは当時と現在とが、まさに共鳴するのである。 平安時代から鎌倉時代への移り変わりは、歴史的必然などというものではなかろう。その革命的な変化は、心の時代から身体の時代への移り変わりだというしかない。私はそう思う。『平家物語』の最後は、壇ノ浦合戦に勝って、都に凱旋してきた範頼と義経が、平家の公達の首を四条の河原に曝すかどうかという議論である。結局は曝すのだが、これがまさに死刑がなかったという「平安」時代の終焉となる。 『方丈記』と『平家物語』の冒頭がよく似ているのは、偶然などではない。あれは日本の中世がはじめて意識化した思想である。思想は恒久だが、身体は無常である。本人はそう思っていないかもしれないが、作家はむしろ身体に触発されて書く。そういうものだと私は思う。玄侑さんはお坊さんだから、それをよく知っている。修行とはもともとそのことだからである。 『方丈記』は短く低声だから、うっかりすると聞き逃す。しかし耳を傾けてよく聞くなら、恐るべきことを語っている書物なのである。玄侑さんの本は、あらためてそれを教えてくれる。読了して、よいお経を聞いた、という思いがある。 |
||
 |
||
| 「波」2011年12月号 | ||